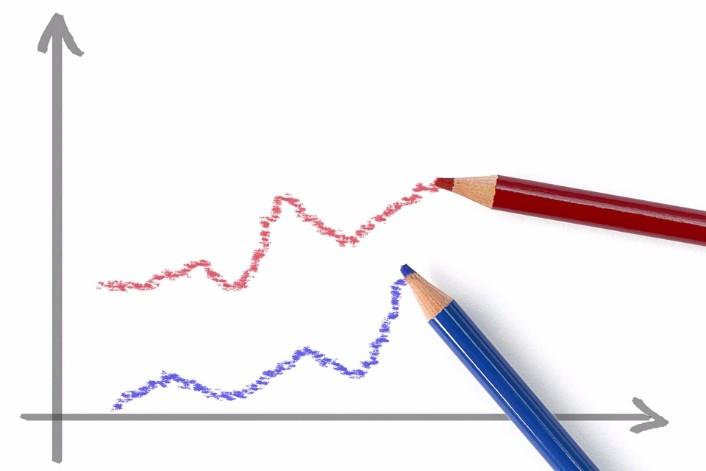ARTICLE
体外受精を検討されている方が心配するのは、母体や産まれてくる赤ちゃんに「リスクはないのか」という点ではないでしょうか。
体外受精は、自然妊娠と違い採卵や移植といった人工的な工程が施されるため、リスクが全くないとは言い切れません。
ただ、自然妊娠であっても流産や障害など、ある程度のリスクはあります。
事前にどのようなリスクがあるのかを知っておくことで、体外受精に踏み切るかどうかの判断材料になるのではないでしょうか。
◆体外受精によるリスクはイメージ的なもの?

体外受精のリスクで多くの人が不安に感じているのは、
「流産しやすい」
「生まれてくる赤ちゃんに障害が出やすい」
といったものではないでしょうか。
しかし、体外受精が直接的な原因で「流産率が上がる」「ダウン症など染色体異常のリスクが高まる」という明確な医学的報告はありません。
一般的に体外受精は、タイミング法や人工授精では妊娠することが難しい方に行われることが多いため、高齢出産になる傾向にあります。
高齢出産の場合、自然妊娠であっても胎児の流産率や染色体異常が発生する確率は上がります。
そのため、体外受精で妊娠すると流産しやすい、もしくは障害を持った子供が生まれやすい、というイメージを持つ人が多いようです。
◆排卵誘発剤による副作用(卵巣過剰刺激症候群)

体外受精では、成長した卵胞を採取する必要があるため、排卵を促すための排卵誘発剤を使用しますが、副作用や胚移植を行う際の影響で、自然妊娠と比べると様々なリスクが生じる可能性があります。
排卵誘発剤によって過剰に刺激を受けると、卵巣が腫れ上がり、重症化すると腹水や胸水が溜まります。
自覚症状には、お腹の張りや腹痛、体重増加、吐き気などが見られます。
軽症であれば、自宅安静もしくは通院で経過観察しながら不妊治療を続けていくことになります。
重症の場合は、入院して水分・塩分を管理するほか、開腹手術が必要になることもあります。
◆多胎妊娠による流産や早産リスク

体外受精による妊娠率を上げる目的で複数の胚を移植すると、多胎妊娠の確率が高まります。
多胎妊娠になると、妊娠高血圧症候群などの合併症や、流産や早産につながるリスクが高くなる傾向が見られます。
双子を妊娠した場合、切迫早産や、帝王切開による出産のリスクが高くなるほか、通常の倍の負担が母体にかかります。
そのため日本産科婦人科学会は2008年に「生殖補助医療の胚移植において、移植する胚は原則として単一とする」という見解を発表。
35歳以上の女性、または2回以上続けて妊娠不成立であった女性を除いては、複数の胚を移植することを原則禁止となっています。
これにより、現在では多胎分娩で生まれる子どもの数は減少し、早産率も低下しています。
◆採卵時の出血・感染へのリスク

採卵を行う際に卵胞まで針を刺す必要があるため、腹腔内に出血が起こります。
たとえ出血しても、そのまま体内に吸収されるのですが、出血が多量になると輸血や開腹手術が必要になることもあります。
また、採卵時に細菌が入り込み、骨盤内感染を引き起こすこともごく稀にあります。
採卵後に強い腹痛や発熱が起こったときは、すぐに医療機関で診てもらいましょう。
抗生物質によって治療が可能ですが、炎症が進み具合によっては、移植を中止しなければならない場合もあります。
◆子宮外妊娠のリスク

体外受精では、自然妊娠よりも子宮外妊娠になる確率が高く報告されています。
子宮外妊娠は、受精卵が卵管や腹腔などの子宮以外の場所に着床して妊娠してしまう症状です。
体外受精では、受精卵を細胞分裂がある程度まで進んだ状態で子宮に戻し、着床するまでの期間を短くできる胚盤胞移植が子宮外妊娠の防止として注目され始めていますが、成功率も決して高くないため、まだまだ定着している方法とはいえません。
◆遺伝子異常などによる男性不妊の遺伝

無精子症や染色体異常など男性側に不妊の原因がある場合、体外受精によって生まれてきた男児に、その男性不妊が遺伝してしまうというリスクがあると懸念されています。
不妊治療が行われる以前は、染色体異常のある精子などは受精することが無かったので、男性不妊が遺伝するということはありませんでした。
体外受精の技術が発達した現代だからこそ、注目されている体外受精のリスクといわれています。
まとめ
体外受精には人工的な手が加わるので、リスクに対して不安を抱くのは仕方のないことです。
ただ、絶対に安全な妊娠はないのも事実で、絶対に回避できる、という予防法もありません。体外受精のリスクに避けるために、体外受精を諦めることは、妊娠のチャンスを逃すことにつながります。
体外受精によって多くの夫婦が子どもを授かっていることは事実であり、自然妊娠であってもリスクがゼロというわけではありません。
体外受精のリスクを恐れるよりも、前向きに取り組むことで妊娠する可能性は広がります。
疑問・不安に感じることがあれば、医師やパートナーとよく相談し、納得のいくカタチで体外受精に取り組んでください。

-
この記事が気に入ったら
いいねしよう!